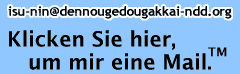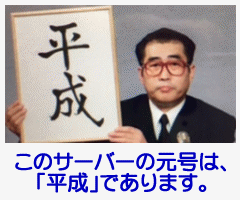
学習センターへの通学手段といえば、地域にもよりますが、 やはり日本では鐡道がいちばんポピュラーでしょう。
でも、通信制の学校の学生生徒は、 学習センターまでの通学定期券を買うことができません。 かといって通勤定期券は値段が高いし、週に4回も5回も通うわけでもないし … というところで皆さん悩まれるわけです。
そんな時に大活躍するのがこれから説明する回数券なのですが、 東京23区内で知り合いとイベントなどに出かけても、意外と皆さん、 回数券を実際に使いこなしてはおられないようで、 当然使うものと思っていた私が逆に驚いてしまうことがままあります。
そこで、回数券についての一般的なトピックをまとめてみました。 例題が東京圏ばかりになっていますが、 これは椅子人が他の地域の事情をほとんど知らないゆえのことですので、 どうかご容赦いただければ幸いです。
多くの鉄道会社が、「回数券」という名前でお得な切符を売り出しています。 ここでは、普通の人が普通に買える回数券について、 そのあらましを簡単にご紹介します。
なお、放送大学と通信制高校の学生生徒 (放送大学以外の通信制大学は不可)は、 普通の回数券よりも安い学割の回数券を買えるのですが、
ほとんどの会社では、回数券は1セット11枚で、発売価格は片道切符10枚分です。 たとえば、150円の区間を行き来するための回数券は、11枚セットで1500円です。
ただし、一部例外があります。いくつか挙げます。
なお、一般的に回数券の有効期間は3ヶ月です。 また、同じ回数券で往路と復路のどちらにも使えます(つまり、 A駅とB駅の間を往復する際に「A→B」と「B→A」の2組の回数券を買う必要はなく、 「A⇔B」の1組でよい)。したがって、 3ヶ月のうちに5往復以上乗れば元がとれる計算になります。
回数券には、「◯◯駅⇔◯◯駅」と駅名が表示されている場合と、 「200円区間」のように金額だけが書かれているものがあります。 一般に前者は「区間式」、後者は「金額式」と呼ばれています。
たとえば、放送大学本部 から成田空港
から成田空港 まで、
JRを使って大人数で移動することを考えます。
このとき買う回数券は、「幕張⇔成田空港 11枚で8400円」となるでしょう。
まで、
JRを使って大人数で移動することを考えます。
このとき買う回数券は、「幕張⇔成田空港 11枚で8400円」となるでしょう。
この切符を使って、幕張駅から乗ることもできますし、途中の千葉駅から乗る (内方乗車 (ないほうじょうしゃ) と言います)こともできます。 あるいは、終点の成田空港駅まで行かずに、ひとつ手前の空港第2ビル駅で降りる (前途放棄)こともできます。その帰りには、たとえば空港第2ビル駅から 「内方乗車」して、幕張で降りることができます。
なお、「自宅が幕張のひとつ先の幕張本郷駅に近いので」ということで、 空港方面からやってきて幕張本郷まで乗り越した場合には、 自動精算機または改札窓口で、 幕張→幕張本郷の140円を追加で払うことになります(もちろん、 幕張⇔幕張本郷の定期券があれば、それを自動精算機に通すだけで済みます)。 空港第2ビルから幕張駅・幕張本郷駅までは840円で同額なのですが、 回数券には幕張までと書いてあるので、 乗り越し精算が必要になるのです。
これを回避するには、最初に幕張本郷駅で 「幕張本郷⇔成田空港」という回数券を買ってくるか、幕張駅のみどりの窓口で事情を話してこの回数券を発行してもらうか、 どちらかの方法をとる必要があります。ただし、JRの駅の窓口は「その駅から出発するきっぷを発売する」というのが一応の原則なので、 幕張駅の窓口で幕張本郷からの回数券を頼んでも、断られる可能性が否定できません。
東京文京学習センター の最寄り駅・茗荷谷と、
東京足立学習センター
の最寄り駅・茗荷谷と、
東京足立学習センター の最寄り駅・北千住との間を地下鉄で行き来することを考えます。
の最寄り駅・北千住との間を地下鉄で行き来することを考えます。
この両駅間の片道運賃は240円で、東京メトロ の回数券は金額式なので、「240円区間」という回数券を買います。
これで、どちらからどちらへも移動できます。
の回数券は金額式なので、「240円区間」という回数券を買います。
これで、どちらからどちらへも移動できます。
さらに、例えば北千住を出て茗荷谷の先の池袋駅まで足をのばした場合も、 この駅間も240円で同額ですから精算の必要はなく、 そのまま改札を通り抜けることができます。
あるいは、こんどは茗荷谷を出発して、北千住方面には向かわず、 東西線で西船橋まで乗ったとします。茗荷谷〜西船橋の片道運賃は280円ですから、 240円の回数券で茗荷谷の改札を通ったのであれば、 西船橋では差額の40円だけを払うことになります。
もちろん、240円区間用の回数券で改札を通り、 170円や200円の区間を乗車して下車することも全く問題ありません。
複数の会社の路線を乗り継ぐ場合、紙の普通乗車券やICカードの場合には、 「乗継割引」といった名前の割引が設定されていることがあります。 しかし通常、2社以上にまたがる、 乗継割引を反映した回数券は発売されていません。
具体例を見てみましょう。
東京文京学習センターの最寄りである東京メトロ丸ノ内線の茗荷谷駅から、
慶應義塾大学三田キャンパス の最寄りである都営地下鉄
の最寄りである都営地下鉄 三田線の三田駅まで移動することを考えます。
駅の運賃地図では310円と表示されています。
三田線の三田駅まで移動することを考えます。
駅の運賃地図では310円と表示されています。
この場合、ルートとしては
これは、東京メトロから出発して都営地下鉄の駅へ、 あるいは都営地下鉄から出発して東京メトロの駅まで乗車する場合には、 合計価格が最も安くなるルート(今回の場合は b. のルート) で東京メトロの運賃 (200円/IC195円)と都営地下鉄の運賃(180円/IC174円) をそれぞれ算出し、その合計から一律に70円を差し引く、 ということになっているからです。
一方で、回数券を使う場合、乗り継ぎの回数券はないので、
メトロと都営のそれぞれ普通の回数券を使ったとして、
a. のルートでは 170/1.1 + 200/1.1 = 354.54円、
b. のルートでも 200/1.1 + 180/1.1 = 345.45円
となり、普通に乗るよりも損をしてしまいます。
このケースでは、後述の土休日回数券を使ってやっと、 普通乗車券よりも安くなります。 具体的には、b.のルートの場合で 200/1.4 + 180/1.4 = 271.43円です。
会社によっては、
普通の回数券よりもさらにオトクな回数券を用意していることがあります。
たとえば、東京メトロや京王電鉄 などでは、
「土休日回数券」「時差回数券」という商品を販売しています
(名称は社によって多少異なります)。
などでは、
「土休日回数券」「時差回数券」という商品を販売しています
(名称は社によって多少異なります)。
土休日回数券は名前の通り、土日・祝日と年末年始のみ利用可能な回数券で、
14枚セットになって片道切符10枚分のお値段、というのが一般的です。
これを使うと交通費が破格に安くなるので、使える人は積極的に使いましょう。
(たとえば、東京メトロと都営地下鉄の土休日回数券を併用すれば、
前節「回数券に乗継割引はありません」で見たように、
乗継割引の効いた普通運賃よりもさらに安くなります。)
時差回数券は、平日の昼間(おおむね10〜16時)に使うための回数券で、 こちらは12枚セットで片道切符10枚分、というのが一般的です。 この時差回数券は、会社によって土日・祝日にも使えるところと、 使えないところとがあるようです。
2015年2月、東京メトロは「一日乗車券」の値下げを実施しました (大人730円→600円、小児360円→300円)。
一日乗車券とは読んで字のごとく、特定の1日間
(正確には、始発電車から、日付をまたいだ25時ごろの最終電車まで)
いくらでも乗り放題というものです。
これは、当日なんの準備もせずに駅にやってきても、すぐに券売機で買えます。
他社でも、たとえばJR東日本 には東京23区内が乗り放題の
「都区内パス」
には東京23区内が乗り放題の
「都区内パス」 という商品があります。これは750円(税8%込)です。
という商品があります。これは750円(税8%込)です。
その日のスケジュールによっては、回数券を何枚も消費するよりも、 一日乗車券を買ったほうがオトクになることがあります。
たとえば私の場合、自宅最寄りの綾瀬駅から東京文京学習センターまでは 240円区間ですので、文京SCに出かけるついでにあともう1箇所、 たとえば池袋に寄っていくことにすれば、 それだけで一日券の元手が回収できてしまうことになります。
というわけでみなさまも、 普段利用している鉄道会社が一日乗車券を出していないか、 ぜひリサーチしてみてください。
追記(11. Jun 2016)
東京メトロは、2016年3月のダイヤ改正から一日券を 「24時間券」と改称し、日付をまたいでも最初の改札通過から24時間まで有効となるように商品内容を変更しました(→プレスリリース
)。
これによって、たとえば下記のようなケースで、 「24時間券」が威力を発揮することになりました。
- 土曜日は学習センターに行きたいが、時間はいつでもいい。
- 日曜日は大きな駅まで買い物に行きたい。 これも時間はいつでもいい。
この場合、土曜日の夕方から24時間券を使い始めれば、 翌日曜日の昼下がりまで1枚で乗れるようになったのです。
これでどこまでオトクになるのか、俄然、楽しみになってきました。
回数券を買ったけど、3ヶ月以内に使い切れない、ということもあります。 そういう場合は、うまく払い戻せるようならば払い戻しましょう。 うまく払い戻せなければ、誰かに売ってしまいましょう。
使用途中の回数券を払い戻すと、次の額が戻ってきます。
払戻額 = 購入額−(運賃定価×使用枚数)−手数料
この計算は、例題を見たほうがわかりやすいでしょう。
東京メトロの200円区間用土休日回数券が8枚残ったとします。この場合、
2000円 − 200円×6枚 − 220円 = 580円なります。意外と低い金額になってしまいました。
このように、残った枚数が少なくて払い戻し額が少ない、あるいは、 計算するとマイナスになるので払い戻しが受けられない、という場合は、
逆に、払い戻し額が大きい場合は、なるべく温存したほうが得です。
たとえば、上記の例題で、7枚目の回数券を使って残り7枚になってから払い戻すと、 払い戻し額は380円になります。 1枚使うごとに払い戻し額はきっちり200円ずつ減っていきますから、 1枚でも温存したほうがオトクということになります。
以上、簡単にまとめてみました。何かお気づきの点がありましたら、
メール(このページの末尾の画像をクリックしてください)かツイッター(@delmonta_iijima)
でメッセージをいただければ幸いです。